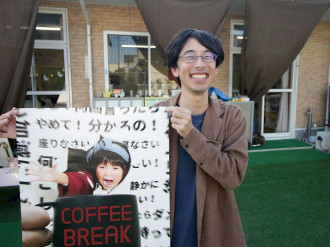「初めての本作り、どうだった?」 岡山市職員がトークイベントで体験披露

トークイベント「はじマルの会vol.1~はじめての本づくり、どうだった?」が4月12日、カフェ「1m2 stand + store(イチヘイベイ・スタンド・プラス・ストア)」(岡山市北区いずみ町6)で開かれた。
トークイベント「はじマルの会vol.1~はじめての本づくり、どうだった?」の様子1
「初めての〇〇(マルマル)」と名付け、誰かが何かを始めた瞬間の話を聞く同イベント。今回は、初めて本を作った公務員の流尾正亮さんと、デザイナーとして本作りにいくつも携わったことのあるデザイン会社「アジェクティブ」の磯野理奈さんを招いた。
流尾さんは会社員を経て、2010(平成22)年から岡山市職員として勤務。現在は文化振興課で、ユネスコ創造都市ネットワーク「文学創造都市おかやま」推進のため、多くの事業を手がける。大学時代にアイルランドに留学した時のことをつづった単行本「シャムロックをさがして」を執筆し、昨年10月に吉備人出版から出版した。
流尾さんは、当時書き残していた日記を縦書きにしたところから始めたという。作家・乗代雄介さんを招いて開催した岡山市の事業「風景を綴(つづ)る・写生文ワークショップ」を生かして、追記や書き直しをして編集者の守安涼さんに提出。そこから約1年後、発行にたどり着いた。流尾さんは「縦書きにしただけでは文章が軽く感じられ、書き直すことにした。『てにをは』の訂正から、言葉の統一など、たくさんの付箋が貼られて返ってきた。どこで終わりにしていいか分からないほど何度も書き直したが、当時感じたことを思い返し、日記に書いた言葉を使ったところがいくつもある」と振り返る。
表紙には、聖書の装飾にも使われる組みひも模様ケルティック・ノットを配し、箔(はく)押しをした。当初は100部を製本したが、1冊当たりの製本価格は販売価格の約4倍かかったという。現在は500冊を増刷して、書店やインターネットでも販売している。
店主の鈴村実咲さんは「今後は花、アロマ、酒など多くのジャンルで話を聞いて、自分もやってみたくなったと言われるイベントを企画していく」と話す。