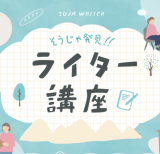岡山県立博物館で「やきものの見方」展 解説文減らし敷居下げて展示

岡山県立博物館(岡山市北区後楽園)で現在、テーマ展「やきものの見方~備前焼から~」が開かれている。
同展は、同館2階の展示室にある美術、歴史、戦後80年、焼きもの、日本刀のコーナーの中から、特に焼きものコーナーをテーマ展として7月3日から開催。展示物を「どこを見ていいか分からない」という声から、作られた時代を見分けるコツなどを、説明文の量を極力少なくして展示する。
展示の始めでは、備前焼の裏側や箱から作られた年代や作家が分かる展示を行う。戦時中に作られた備前焼の手りゅう弾のうち、展示するものの裏側には「11」と印がある。作家ごとに20番までに数字を割り当てられていたが、11番は、後に人間国宝(重要無形文化財保持者)になった山本陶秀(とうしゅう)さんの作品だと分かる。瓦に鳩が2羽止まっているような備前焼「瓦鳩置物」の裏側には、「甲戌(きのえいぬ)秋日、陶陽作」と記してあり、後に人間国宝になる金重陶陽さんの1934(昭和9)年の作品であることが分かる。
次の展示は、高さ1メートルを超える「かめ」3口を並べる。1571年の織田信長の頃、1594年の豊臣秀吉の頃、1613年の徳川家康の頃の3口は、胴の張り方、口の厚み、表面の磨き方など時代によって異なることが分かる。展示品は、時計や指輪を外せば触ることができる。
同館学芸員の重根(しこね)弘和さんは「解説を長く書いても読んでもらえない。博物館のスタッフが見るポイントを、なるべく簡単に解説文を展示した。また見るだけでなく、実際に手で触れてみると、違いが実感できるはず。敷居を下げて、興味を持ってもらえれば」と話す。
展示後半は、「かめ」の形状などが時代によって変化するのと同様に、「つぼ」と「すり鉢」についても時代によって変化する様子がわかる展示としている。その他、桃山時代以降には茶わんや置物などの備前焼も登場し、江戸時代には、「伊勢物語」の東下りのシーンの一つ、馬に乗った男が遠くの富士を見ている様子を備前焼で表現した置物の展示もする。
「見方のコツがわかれば、興味の入り口が広がっていくはず。詳しい解説もQRコードから読むこともできる。夏休みには大人も子どもも、難しく考えずに訪れてほしい」とも。7月19日、8月2日・23日には学芸員の展示解説を、24日には時代を見分けるポイント解説を、いずれも14時~15時に行う。
開館時間は9時~18時。入館料は、大人=260円、65歳以上=130円、高校生以下無料。8月24日まで。