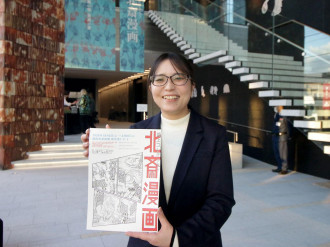岡山県高梁市の備中松山城で3月4日、大池発掘調査現地説明会が行われた。
備中松山城は、高梁市街地の北側・臥牛山にあり、天守は標高430メートルの場所に現存している。現存天守で最も高い場所にあり、冬場には雲海が見られることもある。天守など3棟は重要文化財の指定を受けた日本100名城の一つ。
天守は鎌倉時代、現在とは違う山にあったとされている。同大池はその古い天守から約100メートルの位置にある。文献は少なくいつごろから存在し、なぜ存在したかなど詳細は定かでない。発掘調査は2016年からスタートし、周辺の環境の整備・張り出した木の根を除去・水を抜くなどして大がかりに進められている。
高梁市教育委員会の文化財保護主事である三浦孝章(のりあき)さんは「長方形で、長辺23メートル・短辺10メートルで25メートルプールほどの大きさ」と説明。深さは4.3メートルあり、本来は約2.5メートルまで水が入る。池には水はなく、内部に降りることができた。普段は見ることのできない石垣や遺構などについて三浦さんが解説明した。
初めは、山から流れでる水をせき止めるための溜め池だったが、整備して四角く石垣で囲われた形になっていったとされている。今回の発掘調査で、石垣を補強した痕跡が見つかった。三浦さんは「標高の高い場所で石垣を整えるには、かなりの労力や費用が掛かるはず。それほどまでしてこの池を維持する理由は何だったのか」と話す。
「忠臣蔵で有名な大石内蔵助が備中松山城で働いていたことがある。手紙に、大池をどう活用するべきかに苦心している様子がある」とも。